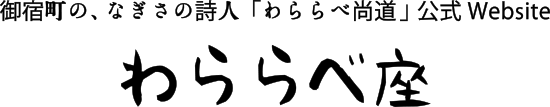短編ファンタジー集|天ぷらしぐれ「川鯉がザブ」④

雨を吸ったせいか少し前から清水老人の服はさかなの臭いが強くなっていることは温郎も感じていました。
「これもしかしてさかなから作ったんじゃ寝えの。なんだいこれは、さばかあじか、それともふぐかなんかかよ。」と二吉が言うと、
「これはさけの皮から私が作ったんだ。おもしろいと思わない会。さけの皮から服ができるなんて。」と清水老人は言いました。
「えっ、さけかよ。ああ、おもしれえ、おもしれえじゃねか。」それをちょっとおれにも貸してくれよ。」と二吉は言いました。
温郎はまずいことになったと思いました。
ところが清水老人は難なく「ああ、いいともさ。」と言うと、さっさとさけの皮の帽子と服を脱いで二吉のいがぐり頭とこんもりと筋肉のもりあがっている肩にかけてやりました。
二吉も少し意外そうに目を細めていました。
「うえい、さけの皮から作った服かよ。」
二吉はそう言うと案外にうれしそうにいっしょに来た仲間に見せていました。
「ああ、けっこうかこいいすよ。お似合いです。」などと仲間の連中が言っています。
二吉は再び清水老人の方を向くとにやにやしながら「これもらってもいいかい。」と言いました。
すると清水老人は「だめだよ。それはできないな。わたしの大切な宝物だからね。」と穏やかな中にもきっぱりとした口調で言いました。
それを聞いた二吉の顔がみるみる紅潮していくのがわかりました。
「おお、聞いたかよ。これがじいさんの宝物なんだってよ。それを聞いちゃますます欲しくなるじゃねえかよ。なあ。」と二吉は同意を求めるように仲間の方を見ました。
すると清水老人がおだやかな口調で「なあ、二吉君。」と言いました。
二吉はいきなり自分の名前を言われて少し驚いたようでした。
「なんだよじいさん。どうしておれの名前知ってるんだよ。ああ、温郎から聞いたのか。」
「ぼくは何も言ってないよ。この人は僕の名前も最初から知ってたんだ。」と温郎が言いました。
「二吉君、もういいよ。そんなに悪者ぶらなくとも。」と清水老人が言うと「おれは別に。」と行って二吉はにわかに落ち着きをなくしたように見えました。
それを見てやはり長年教師をしてきた人は言うことが違う。どんなことばが人の心を揺さぶるのか この人は心得ているみたいだと温郎は思いました。
「二吉君、もういいよ。そんなに悪者ぶらなくとも。もうそんな悪者の振りをしなくてもいいんだから。さっき連絡があったんだ、君の生まれた星からね。」と清水老人は言いました。
清水老人にそんなことを言われて二吉は何かひどく混乱しているようでした。
「お・おれはな・なにもふりなんて。ほ・ほしから連絡ってな・なに言ってるんだ。お・おれはいつもだ・だれに頼まれたってわけじゃ。」
二吉の仲間たちが驚いて二吉の顔を見ているのにも気づかずに二吉はすっかり動揺して小さな声でぶつぶつ言っていました。
「お・おれは別に。だ・だれからも頼まれたってわけじゃあ。で・でもお・おれの星ってな・なんのことなんだ。く・くだらねえこと言うとど・どんなことになるかわ・わかってるだろうな。」
「二吉くん、君が温郎のことをいじめていたのは君の本心じゃないってことぐらい私は知ってたよ。ただ君は悪役を買って出たんだ。なんだって悪役のいない芝居ほどつまらないものはないからね。でもいいんだ。でももう悪役を演じなくともいいんだよ。君の生まれた星から連絡が入ったんだ。お芝居は終わりにしていいってね。」
温郎は清水老人の言うことがにわかに信じられませんでした。そんなことはないだろうと思いました。二吉がこれまでに自分にしたことを振り返ってみてもあれは悪役を演じているとは思えませんでした。何と言っても二吉はそれほど器用な人間ではないことぐらいわかります。
それでも二吉が自分に近づいてくるときに見せるあのうつろで少し陰のあるあの目の光、あれはなんなんだろうと思っていました。
すると清水老人がまた二吉に言いました。
「それよりぼくが作ったそのさかなの服、とても似合ってる。ぼくよりも似合ってる。君が着てる方がきっとそのさけの服も幸せかもしれないね。さっきは返してくれって言ったけど、撤回するよ。それは君にプレゼントしよう。それを着て私といっしょに行くかい。君がうまれた星へ。」
温郎はそのことばに驚いて清水老人の顔を見ました。清水老人はいつのまにか教師の顔になってメがねの奥できらきらと目を輝かせていました。
清水老人はあの瞬間に二吉をいっしょに連れて行くということなのかと温郎は考えました。まさかそんなことはと思いましたがそうは言っても二吉が行くはずはないだろうと思いました。
ところが二吉は「じいさん、おれ生きます。いっしょに行きます。おれ自分の生まれた星ってどんなとこか見てみたいです。」と言うではありませんか。
「そうか、二吉君は行ってみたいか。でももしかしたらここにはもう帰ってこれないかもしれないよ。それでもいいのかい。」と清水老人がたずねました。
「ああ、かまわないさ。おれは絶対に行くんだ。おれが生まれたっていう星にね。」
そう言っている二吉はこれまで一度も見たことのないまっすぐな表情をしていると温郎は思いました。
すると清水老人は今度は温郎の方を向いて
「温郎、おまえさんはどうする。」と聞きました。
老人から改めてそう聞かれると温郎は気持ちがぐらついて自分は本当は何をしたかったのだろうと思いました。そして今まではほんとうにただのちんぴらのようにさげすんでいたのにあんな風にきっぱりと自分の意思を示すことのできる二吉のことがりっぱに感じられてくるのでした。
「えっ、ぼくは、あの、まだそんな。」と温郎はあいまいに心が定まっていないことを言うと、
「そうだな、温郎、おまえはここに残りなさい。それがいい。」と清水老人は言いました。
清水老人にそう言われて、自分だけここに残るのかと思うと温郎は急にさびしくなりました。自分もそのなつかしい場所へ行きたくて
たまらなくなりました。
「やっぱりぼくも行きます。」と温郎が言おうとしたときでした。
突然川でザブっという大きな水音がしてみんな川の方を見ました。
褐色のとても大きな川鯉がはねたところでした。その瞬間それまでどんよりと低く垂れ込めていた雲が裂けて西の空の方から一筋の光が差しました。
それは清水老人の手首ほどもある一本の太さの光の綱でした。
「あ、あれが光のツなというものなのか。」と温郎が驚いて見上げると、いつの間にかその光のつなにぶら下がるようにして清水老人とさかなの服を着た二吉がするすると空へ吸い込まれるようにして登っていくではありませんか。
「ああ、たいへんだ。行ってしまう。」
温郎がそういい終わらないうちに二人の姿は鳥のように小さくなって西の空の奥へと吸い込まれて行きます。
「おおい、待ってくれよ。二吉、ぼくもいっしょに連れて行っておくれよ。」
温郎はそう叫ぼうとしたのですが、まるでのどの奥に何かがつまったように声が出ません。それと同時に逆らいがたい眠気が頭上から霧のように降りてきて温郎の頭にかぶさってきました。だれかに砂金の小さな袋を左右のまぶたの上にそっと置かれたように温郎はもう眠くてたまらなくなりました。
からだも泥のようにずしんと重くなって立ち上がることもできません。手足もからだのわきにはりついたように動かなくなって温郎はまるで地上に放り出されたさかなのように身動き一つできませんでした。そのとき温郎は自分のからだが一匹の褐色の河鯉に変わってしまったように感じました。もう首も以前のように動かすことができないので自分の目で自分のからだを見ることはできませんでしたが、温郎はきっと
そうにちがいないと思いました。
それでも大きく口を開けてなんとか最後にもう一度空を仰いだときには 清水老人と二吉のからだは河原の小石のように小さくなってもうすっかり西の空のかなたへ消えていました。後には薄い桃色の川霧が一筋川もにたなびいているだけでした。
気がつくと温郎は一匹の河鯉になって清水川を泳いでいました。
ああ、とうとうぼくは清水川の鯉になったんだと温郎は思いました。
ひとたび鯉になったからにはもう学校に行くことも家に帰ることもないのかと温郎は思いましたが不思議とさびしい気持ちはしませんでした。
すると水の上の方から何か美しい音楽のようなものが聞こえて来ます。
「なんだろう。あれは。」
鯉になってもやはり温郎はいい耳をしていました。
温郎は水面近くまで上っていって耳をすませました。
「ああ、学校のチャイムだったんだ。」とわかりました。あの楽しそうな人のざわめきが学校のチャイムに混じって聞こえています。
温郎はなつかしい気持ちでいっぱいになりました。もっとこの美しい音を聞きたいと思いました。
そして自分でも気がつかないうちに大きく口を開けて空中に向かって川の中から多角はねていました。その瞬間自分の胸びれと尾びれがすっと手足のように伸びるのを感じました。
温郎は急にからだが軽くなったような気がしてはっとしました。
そして大きく口を開けて胸いっぱいに空気を吸い込むと温郎はいつの間にかベンチに一人で腰掛けていました。
周囲にはだれの姿もなくヨシキリや河鵜やうぐいすの声や葦のそよぎが戻って来て そこは梅雨空が川向こうの家並みに着きそうなほど低く垂れ込めているばかりでした。
(終わり)
川鯉に ざぶと裂けたる 梅雨の空