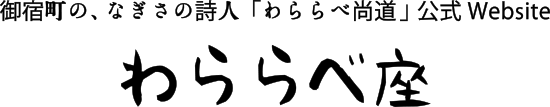海の幼稚園 ①

行儀良く 浪は整ふ 春の海
ぎょうぎよく なみはととのう はるのうみ
1
さよ子さんはホテルのティーラウンジの大きな窓から白い砂浜とその向こうに広がる春の海をながめていました。珍しく風の静かな日で青い波は肩を寄せ合うように横一列になってこちらに向かって打ち寄せて来ます。
その様子を見たときさよ子さんは
「これって何かに似てる。これに似た風景をどこかで見たことがある。」と思いました。でもそれがなんだか思い出せなくて少し沖の方に目をやりました。今日は天気がいいせいか海もおだやかです。
それでもい黒い水鳥が連なるように波乗りをしているサーファーの姿があります。
それを見て
「今日は波太郎君来てないかなぁ。」とさよ子さんはつぶやきました。そしてバッグから群青色をした双眼鏡を取り出しました。
さよ子さんが波太郎と会ったのは一年ほど前のこの場所でした。そのときさよ子さんはとても沈んだ気持ちで海をながめていました。
結婚してもなかなか子供に恵まれないさよ子さんはその数日前に病院で検査をした医師からとても悲観的な報国を受けていたのです。そう言われたときさよ子さんは自分の下腹にぽっかりと暗い空洞があるような気がしてからだがとてもたよりなく感じられたことを憶えています。そんな気持ちをかかえたままあてもなく車を走らせてたまたま目に入ったのがこのホテルのティーラウンジでした。
コーヒーカップを手に海を眺めてはさよ子さんは何度も溜め息をつきました。
「たった一人でもいいから自分の子供が欲しかったなぁ。かわいい女の子だったらずっとよかったのになあ。」とさよ子さんは白くあわ立つている波打ち際をぼんやりと見つめながら何度もつぶやいたものでした。
そのときでした。
「あれ、もしかしてさよ子先生じゃありませんか。」声のした方を振り返ると、近くのテーブルによく日焼けした十八歳ぐらいの若者が
白い歯を見せてこちらを見て笑っています。見覚えのない顔にとまどっていると、
「ああ、やっぱりさよ子先生だ。ぼく亀野波太郎「かめのなみたろう」です。幼稚園でお世話になった。」と若者は言いました。
「えっ、波太郎君。」珍しい名前だったのでさよ子さんはその名前をうっすらと記憶していました。そういえば初めて幼稚園で働き始めたころそんな子供がいたように思います。
でもほんとは亀野君ではなくて亀田君だったかもしれません。下の名前も波太郎君ではなくてなお太郎君のような気もしました。すぐには信じられないことでしたが、でもあれからの歳月を計算してみると確かにそのくらいの歳にはなっていてもおかしくはないのです。
「まあ、波太郎君。こんなに大きくなっちゃって。」
さよ子さんは先生の顔になってとりあえずそういってみました。
「先生、全然かわってないですね」と波太郎君はなつかしそうに言います。
「えっ。そうかしら。そんなことないわよ。」
「そうですよ。でも先生結婚したんですってね。ぼくが大きくなったらぼくと結婚してくれるって約束していたのに忘れちゃったんですね。」
「アッハ、そんなこと私言ったのかしら。ごめんなさいね。」
さえ子さんと波太郎はそんな風にことばををかわすとすっかり打ち解けて子一時間ほど話をしました。波太郎はよくこの浜辺にサーフィンをしに来ているということでした。
「さよ子先生もいっしょにサーフィンしませんか。」
「私はだめよ。水の中は苦手だから。でもここから波太郎君がサーフィンしているのを見せてもらうわ。」
「そうですか。じゃあちょっと波に乗ってくるかな。そのあいだこれを預かっていてもらえますか。」波太郎はそう言うと自分のひざの上に置いてあった群青色の双眼鏡を差し出しました。それは長年使い込まれたものらしくところどころにさびが着いてはいましたがずっしりと頑丈そうなものでした。
「あ、これね。わかった。これでばっちり見せてもらうわね。」さよ子さんはそう言うと双眼鏡を受け取りました。
ところが実際にその双眼鏡を目に当ててみるとまるでまっ暗で何も見えないのでした。
「おかしいわね。もしかしてふたが付いているとか。」さよ子さんは双眼鏡の前の方のレンズを確認しましたがそんなものは付いてはいません。
「ふうん、困ったわね。」
そう言って何気なく望遠鏡を眺める癖で硬めをつむって双眼鏡を眺めたときでした。突然視界が明るくなって見えます、見えます、波太郎がサーフィンをしている姿がはっきりと捕らえられました。まるで大きな波を従えるようにして三角の波の上にすくっと立っている波太郎がさよ子さんの方を見て鳥のように両手を広げて笑って見せています。それを見たときさよ子さんは胸がきゅんとするのを感じました。別に教え子のころの波太郎君のことを思い出したわけではありませんでしたがしばらくぶりに懐かしい人に再会したような気持ちがしたのでした。
「やっぱり波太郎君っていたのかなぁ。」とさよ子さんは思いました。
でもそれから波太郎君はティーラウンジにはもどっては来ませんでした。古い群青色の双眼鏡だけがさよ子さんの手の中に残されたのです。
(2に続く)