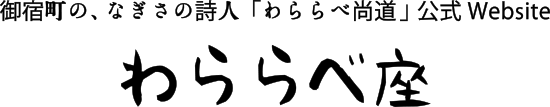あかいカニの家③

③
戦争が終わって十年が過ぎていました。
浩太の家の周りでは古くからの家に混じって新しいかわら屋根の家も建っているのに浩太の家のあった土地はまだくちたがれきが流木のようにそのまま捨て置かれているばかり。それが土と交じり合ってまるで嵐に打ち上げられたオットセイがそのままひからびて黒いかたまりになった様です。
そこだけは周囲とは違っていつまでも時間が流れていないようで、それを眺めるのは浩太には苦しいことでした。浩太はだれかがこの土地を買ってそこに新しい家を建ててくれるといいと思っていました。できればそれは赤いかわら屋根の家がいいと。
それにはあのオットセイを片付けなければと。それで夜になると少しずつくちたがれきを片付けることにしたのです。あまりいっぺんにやってしまうと だれが片付けたのだろうと街の人たちに怪しまれるので少しずつ整理していくことにしました。
浩太はまず大きなはさみをふりあげてオットセイの黒いかたまりをちいさく切断していきました。そしてそのちいさくしたかたまりを左右のはさみに一個ずつつかんで河の土手の地盤がよわくなっているようなところに埋めてゆきました。
今となってはカニは浩太の体そのものでした。カニの太い腕もはさみも浩太の自分の手と変わりありません。カニの足は浩太の足よりも浩太のいうことを聞いてくれます。夜でも水の中でもはっきりとみることのできるカにの大きな二つの目玉は浩太の目といっしょでした。
最近の浩太は自分がカニなのか、カニが浩太なのかその区別がよくわからなくなってきているのです。
一月ほどで仕事は終わり浩太の家のあった土地はさっぱりときれいになりました。その効果だったのでしょうか、少しすると新しい買い手が現れました。
キャデラックを運転して東京からやってきたその人は会社を三つも経営しているという話でした。黒いサングラスをかけてでっぷりとした体格のその人はいつも髪の長いすらりとしたきれいな人を連れていました。
その人が連れの女の人と大工の棟梁といっしょに自分の買った土地に立って話しているのが聞こえます。
そのあいだ髪の長いその女の人は柳の木の下に浩太の姿を見つけて
「あら、こんなところにあかいカニがいるじゃない。かわいいカニさんだこと。やっぱりここは海が近いのね。」と言うと 腰をかがめてしばらく赤いカニを眺めていました。
「洋間は明るい方がいいから窓は大きくして、それから庭は芝生にしてこの柳の木の近くに小さい池でも作ってもらおうかなぁ。」とその人は言います。
「ああ、いいですね。で 屋根はどうします。」と棟梁が聞きます。
「そうさなぁ。屋根までは考えてなかったけど、トタンじゃぁだめかい。」
「だんなさん、この辺は潮風がふくからトタンじゃあ弱いねぇ。かわらじゃないと。」
「ああ、そうか。じゃあかわらにしてもらおう。」
「色は黒でいいですかね。」
「ああ、そうだね。黒のかわらでね。」
その人がそう言ったときそれまで周辺の景色を眺めていた髪の長い連れの女の人が突然二人の方に振り返って言いました。
「わたし赤いかわら屋根がいいわ。ずっと赤いかわら屋根のうちに住んでみたかったの。」
「そうか。赤いかわら屋根のうちがいいか。」とその人は言いました。
それから半年ほどして赤いかわら屋根の家が建ちました。庭は青い芝生がはられ柳の木の近くには小さな円い池が作られました。
浩太は少しずつ家が出来上がっていく間毎日大工や職人の仕事を眺めていました。
そしてとうとう赤いかわら屋根がのった日はなんともいえない喜びでした。
週末になるとその人はキャデラックを運転して髪の長い女の人といっしょに赤いかわら屋根の家に来ます。庭の芝生に白いテーブルを出してバーベキューをしたりお酒を飲んだりします。
お酒に酔うと髪の長い女の人は柳の木の近くにある池に来て浩太の姿を捜します。
そんなとき浩太はなにげない風をよそおって顔を出すのです。
「あら、わたしのカニさん。会いに来てくれたのね。」と髪の長い女の人は大喜びするのでした。
そして浩太に向かって
「わたし こう見えてもけっこう足が太いでしょう。東京の駒込にいたころは鉄くずをのせたおじいちゃんの荷車を押してよく手伝ったものなのよ。」と長いひとりごとを言うのです。
時にはバーベキューに使う高級な牛肉のかけらや野菜のスティックを分けてくれることもありました。
浩太はこの長い髪の女の人が来るのが楽しみになりました。そしてこの髪の長い女の人のことが好きになりました。
この女の人に自分と同じものがあるような気がしたのです。
手足の長いファッションモデルがグラビアから抜け出してきたようなこの女の人の恵まれたからだの奥になにか深い悲しみのようなものが秘められていることを浩太は感じることができました。
しかし赤いかわら屋根の家ができて十年ほどするとその人はもっと若い女の人を連れて来るようになりました。前の人より少し小柄なその女の人はレモン色のミニスカートが好きでなんでもずばずばものを言う人でした。
そして浩太の姿を見かけても
「あら、やだ。こんなとこにカニが。もう少しで踏み潰しそうになっちゃった。」と言って気にも掛けませんでした。
ある日そのレモン色のミニスカートの女の人は「わたし一度でいいからおなかいっぱいにカニを食べてみたいわ。」と言いました。
「なんだ、そんなことお安いことだよ。」とその人は言います。
そしてさっそくたくさんのカニを買ってきて庭のテーブルで食べました。
「おっ、あんなとこにカニがいるぞ。いっしょにゆでて食っちまうか。」とその人は浩太の姿を指差して言いました。
「あら、やだ。そんなのといっしょにしたらせっかくのカニが食べられなくなっちゃう。」と レモン色のミニスカートの女の人はいやな顔をしました。
「ハ ハ ハ ハ。冗談だよ。」とその人は笑いました。
その人の笑顔を見たのはそれが最後でした。それから間もなくして世の中の景気が一遍に悪くなってその人の会社は次々と倒産してしまいました。
赤いかわら屋根の家も他の人に売られてその人も黄色いミニスカートの女の人も二度と来ることはありませんでした。
それから少しして赤い瓦屋根の家のあるじとなったのは 年老いた画家の夫婦でした。画家は八十は過ぎていましたがまだ元気でした。
画家より十は若い奥さんの方がむしろ病弱で 画家は長年の奥さんの苦労に報いるために機構の温暖なこの地に住むことにしたのでした。
画家は柳の木の下に浩太を発見すると
「おお、こんなところにカニがいるぞ。ううん、このカニはなかなか趣のある顔をしているじゃないか。」と言ってすっかり気に入ってしまったようでした。
そしてさっそくスケッチブックを取り出すと浩太のことを写生し始めたのでした。
画家はたくさんカニの絵を描きました。そしてその中の何枚かは展覧会でも評判になって画家の名を高めました。出版社の物好きな人間はわざわざ画家の赤いかわら屋根の家まで訪ねてきて絵のモデルになった浩太の写真を撮っていきました。
しかしその画家の夫婦も八年ほどで赤いかわら屋根の家を出て行きました。
病弱だった奥さんが亡くなったのです。他に身寄りのない画家は知人の多い東京の馬込に元々ある自分の家へ帰っていきました。
年老いた画家に代わって赤いかわら屋根の家の持ち主になったのは 二人の小学生の男の子のいる家族でした。生命保険の会社に勤めているだんなさんは隣町の支店長に転勤になって来たのだという話でした。
「前から海の近くに住んでみたかったんだ。それに子供たちにもいい思い出になるしね。」と だんなさんは髪をポマードでびしっと固めた不動産屋に言いました。
「奥さんにもたいへん気に入っていただいてなによりです」と不動産屋は言います。
まだ空に充分な明るさが残っている夏の夕暮れでした。
本当に久しぶりに赤いかわら屋根の家に元気のいい子供たちの声が響きました。
「そんなきたない足であがっちゃだめでしょう。そこにぞうきんがあるからちゃんとふいてからあがりなさいよぉ。」と言うお母さんの声も聞こえます。
「なんだかあの声を聞くとお母さんのことを思い出すなぁ。」と浩太は柳の木の下から新たな家の住人たちを眺めながらつぶやきました。
こういう家族が来てくれるのを長いこと自分はずっと待っていたんだと思いました。
庭で遊んでいた男の子はとうとう柳の木の下にいる浩太を見つけました。
「わあ、こんなところにあかいカニがいるよ。」と弟の方が言います。
「ほんとだ。どっから入って来たんだろう。ぼくんちのうちに。」とお兄ちゃんの方が言います。
二人は浩太のことをしばらく遠巻きに見ていましたがやがて近くの草の茎を折ってそれでおどかしたりそれでもたいして動かないのを見て
指先で突っついてみたりしました。
浩太は二人の男の子のいたずらから逃げ出したかったのですがからだがどうにも重くて足を素早く動かすことができませんでした。それでも懸命に柳の木の陰の方に逃げ込もうとすると
「おにいちゃん、このカニなんだかよろよろ歩いてるよ。」と弟の方が言いました。
「ほんとだ。こいつおじいちゃんみたいなカニだな。」とお兄ちゃんの方が言って
「おじいちゃんカニ、おじいちゃんカニ。」と二人は大声ではやし立てました。
それからさらにこどもらに追い立てられて浩太はそばの小さい池の中に飛び込みました。小さな水しぶきがあがって兄弟は「わあっ」と言って飛びのきました。
そこに「何やってるの、ご飯ですよ。」と言ってお母さんが様子を見に来ました。
兄弟が口々に赤いカニを見つけたことや追い掛けていたら池に飛び込んだのだというようなことを言いました。
「まあ、なんてひどいことを。小さな生き物をいじめたりして。」と彼女は言いました。
浩太はそのことばにうれしくなりました。それでどんなお母さんなんだろうと目をこらして彼女の顔の方を池の中から見上げました。でもけっこう近くに立っているその人の顔を浩太はしっかりと見ることができませんでした。
最近なんだか目の前が霧がかかったように白くぼんやりしてよく見えないのです。
戦争が終わって三十年が経っていました。
「でもお母さん、このカニがかってにぼくんちのとこに入って来たんだよ。」とお兄ちゃんの方が少し不服そうに言います。
「まあ、なんてことを。」と彼女はあきれたように言いました。
「この庭にはおまえたちが生まれるずっと前からカニが来てたのよ。じつはね、お母さんは子供のころここに住んでいたことがあるの。そのころからうちの庭にはカニが来てたのよ。」と彼女は言いました。
「へぇ、そうだったんだ。すごい偶然だね。」弟の方は感心したように言います。
「偶然じゃないのよ。お父さんがいろいろ調べてここが売りに出てるのを見つけてきてくれたのよ。」と言うと彼女はほほえみました。
「でもお母さん、どうしてここから引っ越しちゃったの。」とお兄ちゃんの方が聞きました。
「戦争があったのよ。」と彼女は言いました。
「家に爆弾が落ちてお母さんのお兄ちゃんと両親が亡くなったの。わたしももう少しで死ぬところだったのよ。そのときこれは後で近所の男の人から聞いた話なんだけど大きなあかいカニが飛び出してきて火の中からわたしを救い出してくれたんだって。」
「へぇ、すごい。」とお兄ちゃんは驚いて目をばちくりさせながら池の中の浩太の方を眺めてちょっと首をかしげました。
「お母さん、それテレビの人に話してみたら。きっとテレビ局の人がうちに話を聞きに来るかもよ。」と弟の方が言ったので、彼女はくすっと笑いました。
浩太は驚きのあまり声も出ませんでした。白くぼんやりと霧のかかった視界の中に記憶の中の小さなころの妹の顔がくっきりと浮かび上がります。
「お兄ちゃん、今見たら柳の下にあかいカニがいたよ。」
「えっ、柳の下。そりゃあたいへんだ。このまま放置しておくわけにはいかん。さあ、行くぞ。」
昔この庭で幼い妹のさやと交わしたことばの一つ一つがよみがえってきます。
「さあ、ご飯にしましょう。」
彼女はそう言うと男の子たちを連れて家の方に歩き始めました。
「ねえ、いつもよりごはんが早いんじゃないの。」とお兄ちゃんが聞いています。
「そうよ。ご飯を食べたらあとでお寺にいくのよ。」という彼女の声がしだいに遠ざかりながら聞こえています。
「やっぱりテレビ局の人に話した方がいいよ。」と言う弟の声もまだ聞こえています。
三人の声がすっかり聞こえなくなってしまうと浩太は意識がしだいに遠ざかっていくのを感じました。白くぼんやりとした視界が一瞬快晴の空のように晴れ渡ったかと思うと、ゆっくりと幕を下ろしたよううに目の前が暗くなっていきました。
気がつくと浩太はカニの中の運転台に腰掛けてうとうとしていました。
そのときだれかが甲羅の壁を叩く音がしました。
その声は「ここを開けて遅れよ。」と言っているようでした。
「そのとびらはだめなんだ。」と浩太は思いましたが、あまり何度もたたくので浩太はとびらの前に言ってそっと押してみました。
するとなんとも感嘆に開いたではありませんか。
とびらを開けて入って来た人の顔を見て浩太は「あっ」と言いました。
その人は賢治兄さんでした。
「兄さん、どうして急にいなくなったりしたの。あれからもう三十年だよ。」
浩太はとっさにそんなことを言っていました。
すると兄さんは
「えっ、そんなにたってる会。うそだろう。昨夜会ったばかりじゃないか。今夜はちょっと用事があって遅れてしまったんだよ。」などと言います。
その言い方があまりにも間違いないという感じで言ったので
「えっ、そうなんだ。まだそんなものだったのかな」と浩太は一瞬考えてしまいました。
「そうなんだ。まあいいや。日が落ちたらまたいっしょにでかけようよ。昔二人でいろいろと夜の街を探検したみたいに。」と浩太が言うと兄さんは静かに笑って
「浩太、今夜はここから出て二人で海を見に行くんだよ。なんたって今夜の海ときたらまるでエメラルド色のガラスを敷き詰めたみたいにきれいなんだからね。さあ兄さんといっしょにここから出るんだ。」と言って浩太の腕を優しくつかみました。
「でも兄さん、ここを出たらいったいどうやって。」と浩太が言いかけると
「浩太、なんの心配もいらないからね。そこの河に舟を繋いであるんだ。それに乗って
兄さんといっしょに河を下って海に出るんだ。それはそれは広い海だよ。そこで兄さんといっしょにいろんなところを探検しようよ。」と
賢治兄さんは言います。
「えっ、それはすごいよ兄さん。じゃあ今から用意するから明日で掛けようね。」
「いや、今でかけるんだよ。」
「でもそんな急に言われてもさ、いろいろと準備しなくちゃいけないしね。」と浩太は言いましたが、
「準備なんて何もいらないんだよ。」なにか持って行くものでもあるのかい。」と聞かれると、浩太は何も言えずにそういえば何の準備もいらないような気がしてくるのでした。
「えっ、ずいぶん急な話なんだね。」
浩太は外へいっしょに出られるのがうれしいくせにこのカニのからだからすっかり出てしまうのがさびしいような気もしてすぐに腰を上げられずにいました。
しかし兄さんから
「さあ、行くよ。」と声をかけられると
「すぐ出なくちゃいけないのかな。」と聞いていました。
「うん、なんてったって舟をあんまり長いこと待たせておくわけにはいかないからね。」と兄さんが言ったので
「ああ、そうか。そりゃあしかたがないよね。わかった。じゃあ今すぐに出るんだね。」と言ってうなずきました。
浩太は運転台から本当に久しぶりに立ち上がりました。
少しふら付いていましたが兄さんがそっと手を貸してくれました。
兄さんにとびらを開けてもらって浩太は久しぶりに外に出ました。夜の潮風がたちまち浩太のからだを包みます。
「ああ、涼しい風だね。なんて気持ちがいい風なんだろう。こんな風に吹かれるのはもう三十年ぶりだよ。」と浩太は言いました。
「またそんなこと言ってる。」と兄さんは笑っています。
それから河に出て兄さんの用意した舟に乗りました。
ゆっくりと河を下りながら浩太が街の方を眺めると 灯をともした提灯を下げた人が何人か夜の路を歩いていく姿が見えました。
その中には妹のさよの家族の後姿もあります。
「あれはなんだろう。」と浩太が提灯の灯を指差して兄さんにたずねました。
「ああ、今夜はお盆の送り火なんだよ。」と兄さんが言います。
「はあ、そうだったんだ。」と浩太は思いました。
「ほら、海が見えてきた。広い広い海だよ」と言って兄さんが前方を指差します。
沖の方ではどどーんと大砲で青い砲弾を撃つように 波の音が何度も繰り返しとどろいていました。
船は油の上をすべるように沖へ向かって進んでいきます。船足はますます速くなって正面から潮風が浩太のからだをすっぽりと包むとそれはまるで新しい風の衣服をまとっているかのようでした。
終わり
雲垂れて 路地に湧き出す 蟹の赤