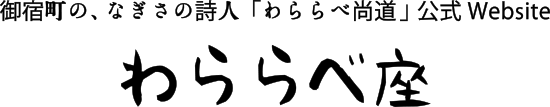海の幼稚園③

3
さよ子さんがこのホテルのティーラウンジに来たのは久しぶりのことでした。
一年前に沈んだ気持ちをかかえてここに来たとき思いがけずに波太郎と出会って さよ子さんは明るい気持ちになれたことを憶えていました。
あれからしばらくさよ子さんは波太郎からあずかった群青色の双眼鏡を持って たびたびこのホテルのティーランジから海をながめたものでした。
あの双眼鏡には何か不思議な力があるようでした。さよ子さんがそれで海を見ていると一度も子供なんて
生んだことのないのにまるで自分がこれまで何十人も子供を生み育てた母親になったような気持ちになるのでした。
例えば浜辺に一見雑草のように生えている草花の一つ一つまでが何かいとおしく感じられてくるのです。
波太郎とはあれ以来一度も会ってはいませんでしたがさよ子さんはあれから気持ちをなんとか立て直してがんばることが出来たのでした。
私には一生子供は恵まれないかもしれないけれど、波太郎のように幼稚園がさずけてくれたたくさんの子供たちがいるじゃないのと考えるようにしたのでした。
実際さよ子さんにとって幼稚園の子供たちの一人ひとりは命の光輝く存在以外の何者でもなかったのです。
しかしなんとか気持ちを立て直すことができたと思ったのもつかのま再びさよ子さんを失望させる出来事が起きたのでした。
それはさよ子さんが今働いている幼稚園が三年後に廃園してしまうことに決まったのです。そんなうわさを聞いても最初はほんとうにはできませんでしたが、いよいよ先週園長さんからその話を聞かされてもうだめなんだということがわかったのでした。
「ほんとにこの世の中に神様なんているのかしら。」とさよ子さんは思いました。
この数年というもの幼稚園に入ってくる子供の数がめっきり少なくなって来たのは確かでした。地方の海辺の小さな町では市の保育園の他にもう一つ私立の幼稚園を経営していくのはむずかしい時代になってきていたのです。
さよ子さんは手にしていた群青色の双眼鏡を眼に当てて沖の方をながめてみました。波がおだやかなせいかサーフィンをしている人はちらほらと数える程度です。今日は若い女性のサーファーが多いなとさよ子さんは思いました。
それからそういえば波太郎から「先生、いっしょに波乗りしませんか。」と誘われたことがあったっけという記憶がよみがえりました。あの時はとてもそんな気持ちにはなれなかったけれどもしもあのときいっしょに海に出て波太郎からサーフィンを教えてもらっていたら自分の世界ももう少し広がっていたかもしれないと思いました。
そのときです。浜辺の波打ち際の辺りで潮騒に混じって「ワァワア、ワァワア」という子供たちの歓声を突然聞いたような気がして さよ子さんは双眼鏡を眼から外すと窓から浜辺の声のした辺りを見回しました。
しかし子供たちの姿はもちろんさっきの歓声のようなものも全く聞こえません。
ただ以前のように波の音が規則正しいリズムを刻んでいるばかりです。
「あれ、さっきのは空耳だったのかしら。確かに子供たち、それもどちらかといえば小鳥がいっせいにさえずっているような小さな子供たちのあの明るい声を聞いたような気がしたけれど。
へんね。わたしおかしくなっちゃったのかしら。」とさよ子さんは首をひねりました。
それからまた気を取り直して双眼鏡を目に当てました。
するとまた「ワァワア、ワァワア」というさっきの子供たちの声がまた浜辺の波打ち際の辺りから潮騒に混じって聞こえてきます。
「あら、おかしい。」
あわてて双眼鏡を目から外して浜辺の声のした辺りを見回しましたがやはりそんな姿はもちろんこどもたちの歓声もまったく聞こえません。
それからさよ子さんははっとしました。
「あのこどもたちの声ってこの双眼鏡で海をながめているときしか聞こえないのかしら。」と思ったさよ子さんは耳をすませて双眼鏡を目に当ててみました。
すると「ワァワア、ワァワア」という幼いこどもたちの歓声が双眼鏡の中から聞こえてくるではありませんか。
「ううん、やっぱりそうみたいね」とさよ子さんは何度かためしてからはっきりと確信しました。
それからこれはどういうときによく聞く声だっけと考える間もなく思わず笑いがこぼれました。
「そうだ、この子供たちの声。毎朝子供たちが幼稚園の門をくぐって入ってくるあのときの声じゃない。そうだ。そうだ。」と さよ子さんは思いました。
「これはいったいぜんたいどこの幼稚園なのかしら。ああ、声はすれども姿は見えずとはこのことね。さよ子さんはおいしそうな臭いはするのに肝心の食べ物がどこにあるのかわからないようなじれったい気持ちになりました。
そのときです。背後でさよ子さんを呼ぶ声がしました。あっと思って振り返ると波太郎がそこに立っていました。
「あら、波太郎君。来てたんだ。」
さよ子さんはなんだかうれしくなって波太郎にほほえみかけました。
でも今日の波太郎の笑顔はなんだか曇っている感じでした。
「おや、どうしたの。」とさよ子さんがたずねると波太郎はなんだか少しあせった様子でさよ子さんに言いました。
「先生、今すぐにぼくに協力してほしいことがあるんですけど。」
「協力、何かしら。私にできることなら。」
さよ子さんに最後まで言わせないうちに「波の子を救ってあげたいんです。先生にも手伝ってほしいんです。」と波太郎は言います。
「波の子ってつまり波の子供ってこと。でも波の子ってなにそれ。よくわからないんだけど。」
「さよ子先生、波の子がこの浜辺にある海の幼稚園に入るためにこっちに向かってるんです。」
「えっ、波の子の幼稚園。どういうこと。ぜんぜんわからないんだけど。
波太郎君、落ち着いて話してみて。」
さよ子先生はそういってすんだまなざしでまっすぐに波太郎の目を覗き込むようにして優しく言いました。こうしてさよ子さんが話かけてやるとたいていのこどもたちは落ち着きを取り戻すのです。
「ああ、すみません。さよ子先生。こんなこと行って信じてもらえるかどうかわからないんですけど、実は波にも命があるんです。だから波にも子供がいるんです。」
「こども。だから幼稚園ってことね。」
そのときさよ子さんの耳にあの双眼鏡を覗き込んだときに聞こえたこどもたちの歓声がよみがえりました。
「もしかしてあれが波の子たちの声だったのかしら。」
「あっ、さよ子先生にも聞こえていたんですね。そうです、そうです。あれが波の子たちの声なんです。」
「でも声はすれど姿は見えずなのよ。どこにいるの。その波の子たちって。」と さよ子さんが言うと、波太郎はさよ子さんが手にしていた群青色の双眼鏡を手に取って「この広いレンズの方を目に当てて見てくれますか。」と言っていつもとは逆の方をさよ子さんの目に当てました。
そのやり方で海の沖の方をながめた瞬間さよ子さんは「あっ。」と声をあげました。
そこに見えたのはこれまでに見たことのない海の風景でした。
それまで群青色をしていた波間は緑の牧場に、サーファーたちを乗せていた深い青色の波はしろや青色の馬にかわっていました。
それまで波がつかのまに作り出していた波の形はみな生き物となってあるものは犬やねこに、あるものは草花やサクラやイチョウの木になっていました。
そして幼稚園も確かにあったのです。
そこはもっとも陸に近い場所でした。波が寄せてはかえすぬれた砂浜のあたりに小さな幼稚園がありました。さんごの石垣に囲まれて庭にはブランコや木馬が置かれ もちろん砂場もありました。それらが光の海に包まれてまばゆいエメラルド色に輝いているのです。
そしてさよ子さんがずっとはるか遠くの方を見ると、沖の方に十人ぐらいの幼い子供たちが互いに手をつないで横一線になってこちらに向かって走って来る姿が見えました。水の上にふわりと腰掛けるようにして乗っているのはよく見ると一輪車のようです。
「まあ、なんてかわいい子たち。」とさよ子さんは叫んでいました。
特に列の真ん中あたりで大きく手をふっている女の子の姿を見たときさよ子さんは不思議な気持ちになりました。親戚の家かどこかで見たことがあるような、いやもっとはっきりとこの子のことわたし知っているという気がしました。
そのときさよ子さんははっとしました。
「あの子たちあんな勢いで一輪社を走らせてきたらきっと幼稚園の石壁に衝突してしまうんじゃないかしら。
そう思ったときさよ子さんは双眼鏡を持ってホテルのティーラウンジから浜辺へ飛び出していました。
「波太郎君、シャベルかなにか持ってたらここに持ってきて。」とさよ子さんは言いました。
「はい、すぐに。」という波太郎の声が背後で聞こえました。
さよ子さんは双眼鏡を眼に当てて幼稚園のある場所を確認しました。
そして波にぬれた砂浜の一郭に立ちました。
「ちょうどこの辺じゃないかしら。」とさよ子さんが言いました。
「そうですね。このあたりでよさそうです。」と さよ子さんから受け取った双眼鏡を目に当てた波太郎が言いました。
それから二人はそこに小さな砂のすべり台を作り始めました。
滑り台といってもしだいに高くなってから緩やかに降りていく滑り台です。
ちょうどおとなの腰の高さほどのすべり台を全部で十個作ることにしました。
波太郎が大きなシャベルで砂をもるとさよ子さんが小さなシャベルですべり台の形を作っていきます。
そして二人は交互に双眼鏡で海の様子を確認しました。りん子たちの姿はしだいに大きくなってこちらに近付いて来るのが見えます。
「まあ、たいへん。急がないと。」と さよ子さんは言いました。
「えっ、今どのへんに来てるの。」
今度は波太郎が双眼鏡を目に当てると「あ、こりゃあたいへんだ。もうすぐ来るぞ。」と言いました。
二人は砂のすべり台を作りながら双眼鏡をながめ、双眼鏡をながめては砂のすべり台を作っているうちに、今自分が双眼鏡で海を見ているのか双眼鏡を当てずに見ているのかわからなくなりました。
そして気が着くと二人は双眼鏡を使わなくともりん子たちの姿が見えるようになっていました。
おとなの足が立つほどの浅瀬までりん子たちが近付いてきたときようやく十個の砂のすべり台が歓声しました。
二人はどっと疲れて砂の上にぺったりと腰を下ろしました。そしてはあはあ息をしながらすぐそこまで手をつないで横一列に並んで水の一輪社をこいているりん子たちの姿を見ました。
りん子たちは「わあい、海の幼稚園に着いたぞおい。」と歓声をあげながら砂のすべり台の上に乗り上げました。ざざつと砂をかき分ける音がしてりん子たちの一輪社は無事に止まりました。
それからりん子たちはさよ子先生の姿を見つけると
「わあい、先生がそこにいる。海の幼稚園の先生だよ。」
そう言ってさよ子さんの方に一輪社を降りて駆け寄ってきました。
さよ子さんも立ちあがるとおしりの砂をはたいて子供たちを胸に受け止めるために両手をさゆうに広げました。
りん子たちがさよ子先生の胸にめがけて走り寄ってきます。
「わあい、さよ子先生だ。」
列の真ん中にいた女の子がそう叫んでいるのが聞こえました。
「りん子ちゃん、いらっしゃい。」とさよ子先生もなぜかそう叫んでいました。
そのときさよ子さんは胸がきゅっとしめつけられるようなせつない気持ちがしました。
遠い遠い昔、それはもしかしたらまだ自分が生まれるよりさらに遠い昔のこと、さよ子さんは自分がこの浜辺で子供を生んだことがあったような気がしたのです。
月夜の晩に浜辺の片隅に作られた小屋の中で天井から吊り下げられた太い綱につかまりながらたった一人で女の子を生んだことがあったような気がしたのです。
気が着くと、辺りはすっかり夜のように暗くなっていました。子供たちの歓声も消えて辺りはしーんと静まり返りました。
蒼い月の光たけが暗い夜の雲間からさよ子さんの足元に一筋差し込んでいました。
でもそれもつかの間少しすると昼間の明るさが返って来ました。
それまで消えていた潮騒の響きももどって来ました。
やがて周囲が元どおりの明るさをとりもどしたときにはさよ子さんはたった一人で春の日差しが降り注ぐ浜辺に立っていました。
そこには波の子たちや海の幼稚園や緑の牧場もなく以前の青い海原だけが広がっているばかりです。
さっきまでいっしょに砂のすべり台を作っていた波太郎の姿もどこかに消えていました。
さよ子さんは我に帰るとあわてて双眼鏡を目に当てました。
でもやはりそこに見えるのは沖の方でまばらにサーフィンを楽しんでいる海の風景でした。
そのときさよ子さんの足元に向かって青く輝いた波が横一列に行儀欲肩を
並べるようにこちらにむかって打ち寄せて来るのが見えました。
さよ子さんは腰をかがめて静かに打ち寄せてくるそのエメラルド色に輝いた波を両手で掬い取りながら言いました。
「さあ、いらっしゃい。今日から私が海の幼稚園ですからね。」
(終わり)
行儀良く 浪は整ふ 春の海