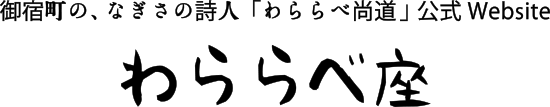短編ファンタジー集|天ぷらしぐれ「川鯉がザブ」①

川鯉に ざぶと裂けたる 梅雨の空
かわごいに ザブとさけたる つゆのそら
そこは外房の海辺の小さな町に流れている川のほとりでした。梅雨空が川の向こうの屋並にとどきそうなほど低く垂れ込めています。
中学からの帰りに温郎が川沿いの小道を歩いていると川の方から突然ザブと音がして何だろうかと思ってみて見ると 丁度褐色の大きな鯉が跳ねたところでした。それはまるで水の面を布団でもめくるようにひっくり返したみたいで いつになく大きくみごとな音は その姿を見ずに音だけ聞いていたらきっと小さなイルカのスナメリか何かが跳ねた音のように思えたくらいでした。
「はあ」と温郎はその場に足を止めると大きく口を開けたまま鯉の跳びこんだ波立っている水面のあたりをながめていました。なぜかそのときだけは今までせわしく鳴いていたヨシキリや河鵜やうぐいすのさえずりも川沿いにびっしりと生えている芒のそよぎもピタリとやんで近くの橋を通り過ぎる車の音もとだえて周囲は静まり返っているのでした。
西の方の空から一筋光が差したような気がして 温郎は低く垂れ込めた空を少し視線を持ち上げて見上げてみましたが 空は川のおもてを写したようにどんよりと曇っているばかりでした。
「おかしいな。今どこからか光が差したような気がしたんだけどな。気のせいだったかな。」と温郎は思いました。
やがてヨシキリや河鵜やうぐいすのさえずりや芒のソヨぎが聞こえてきて、橋を行き交う車の音がもどってくると温郎はまたゆっくりと歩き始めました。
なだらかな坂道を少し下るとそこに木製のベンチがあります。清水川という小さな川ですが この川べりの小道は町の遊歩道にもなっているのです。
温郎は中学校からの帰りによくそのベンチに腰掛けて物思いにふけったりするのでした。ときどき風に乗って中学校のチャイムの音が聞こえます。そういうときはチャイムの音に乗って女子による校内放送の声やその背後のざわめきまでも聞こえてきたりします。
そんなとき温郎はそういうものを呼吸といっしょに吸い込むように自分でも知らないうちに大きく口を開けて聞いているのでした。大柄で丸顔の温郎がぽかんと口を大きく開けているのを見てクラスの連中からはこいのぼりというあだ名を付けられたくらいです。そして自分でもはっとしてそのことに気づくとまるで今自分はあくびをしていたというように手を口に当ててあわててごまかすのでした。
温郎は小さなころから人の話し声や笑い声を遠くから聞くのが好きでした。
そのざわめきはいつも幸福そうな楽器のエチュードのように聞こえるからです。
「ああ、なんだって人の声っていうのはみんながみんな一つに重なり合うとこんなに美しい音になるんだろうか。」と温郎は思うのでした。
ところが温郎は小さい頃から人なかに入ってどしどし自分のことを話したりするのが苦手でした。それはただの引っ込み思案というのではなく 自分はこの世界にとても慣れていないという感じがいつもあるのでした。
温郎がいつもそうかんじているせいか周囲からも何を考えているのかよくわからないやつという風に見られているようでした。
そんな温郎にとってときどき自分の気に入った場所で一人になって物思いにふけるのは唯一の息抜きでした。そしてこの川沿いの小道や道の端に置かれたベンチは温郎のお気に入りの場所なのでした。
しかし今日はだれかがもう先にそのベンチに腰掛けて川をながめているではありませんか。
温郎は内心舌打ちして少し弓なりになっている小道を下っていきました。
ところがそのベンチの人影をはっきりと視界に捕らえたとき温郎はあっと声をあげそうになりました。
なんともそこにいるのは上半身が魚で下半身が人間といった様子の半魚人ではありませんか。
温郎は途中で足を止めて傍らの木の陰に身を入れると顔だけそっと出してその半魚人の人影を見ました。
するとどうやらそれは温郎の見間違いだと知れました。上半身がさかなだと思われたのはさかなのうろこに似せたごわごわした感じの上着とやはり魚の頭をかたどった帽子をかぶっていたせいだとわかりました。
それでもよく見ると丸いメガねをかけていましたが、それが遠めにはかえって魚眼レンズのように感じられたのでした。
温郎には人の年齢というものがよくわかりませんでしたが それでももうかなりの歳だということだけは顔のしわから想像できました。
とにかく半魚人でないことはわかりましたがそれでもなんだか気味が悪いことに 代わりはなかったので温郎はどうしたものか迷いましたが引き返して遠回りをするのもめんどうなので結局そのまま歩いて行くことにしました。
川をながめなから歩いている風を装ってできるだけベンチの方は見ないようにして歩いて行きましたがさかなの老人が腰掛けているベンチの前を少し通り過ぎたと思ったあたりで温郎は一度だけちらりとベンちの方を見てしまいました。
そしてそのときさかなの老人と目が合ってしまったのです。
さかなの老人は口のはしをかすかに上げてにやりとすると「温郎。今日はまっすぐ帰るの会。」と言ったのでした。
温郎は跳び上がるぐらいびっくりして足を止めるとさかなの老人の方を見ました。
「いつもこの時刻にはこのベンチにこしかけて川を見てるんだろう。すまないね。
ついつい長居をしてしまったようだ。今日はあんまりいい日和なものだから。さあ、私はもう行くからここにすわっておくれ。」とさかなの老人は言います。
温郎は返事に困りました。それは全く思いがけないことばでした。
温郎は家でも学校でもどこでもこんな風に自分の居場所のことを大切に扱ってくれる人を知りませんでした。温郎の周りの人間ときたらだれでも自分の用件だけをずけずけ言うばかりで温郎の居場所のことなど一向に気にも留めていない連中ばかりなのです。
「はあ、どうも」
温郎はあまり気が進まなかったのですがさかなの老人のことばに引き寄せられるようにベンチの前で足を止めていました。もちろん老人の言うとおりにこのベンチに腰掛けてみてもいつもののんびりとした気持ちにはなれないような気がしましたがそれでもその申し出を断ったらなんだか老人に悪いような気がしたのです。
それにどうしてこの人は温郎という名を知っているのかということも少し気になりました。
そんなことがいろいろと一度に頭にめぐったせいでしょう。温郎は自分でも思いがけない返事をしていました。
「おじいさん、別に行かなくてもいいですよ。ここに座っていてください。ぼくは隣に座りますから。」
そう答えてしまってから温郎は「ああ、失敗したぁ。なんてことを言ったんだ」と思いました。
「そうかい、悪いね。」と言うと、
さかなの老人は思いがけない軽い身のこなしでベンチの端に座り直すととなりをもう指差しています。しかたなく温郎は老人のとなりに座りました。
さかなの老人のからだからはさかなのひもののようなにおいがうっすらとしました。
温郎が鼻をひくひくさせているのを見て「ハハァ、さかなくさいかい。これでも前よりはずいぶんましになったものだよ。なんたってこれはさけの皮から作った服だからね。」と さかなの老人は言いました。
老人の話ではこれは昔アイヌと呼ばれた人たちがさけの皮から作った服を着ていたという話を何かの本で読んで自分で作ってみたのだということでした。
「アイヌって北海道の人でしょう。ここにもいたんですか。」と温郎が聞くと「ううん、ずっと昔には日本の本州から九州までいたんじゃないのかな。
だって温泉で有名な大分県の別府っていう地名ももともとはアイヌのことばだったっていう話だからね。」
「おじいさんはそういうことを研究している人なんですか。」と温郎が聞くと、さかなの老人は胸の前で手を横に振って
「いやいや、何も研究なんてしてないよ。わたしは好き勝手なことにいろいろ頭をつっこんでやってるだけなんだ。」と言いました。
さかなの老人は清水という名前で昔この町で中学の教師をしていたそうです。もっとも退職してからずいぶん歳が経っているので最近の学校のことは全然しらないということでした。
この近くに猫のひたいほどの畑を借りていて日曜菜園をやっているのだという話です。
清水老人はそういうとベンチの後方を振り向いてちょっと小道を下った所にあるそら豆が白い花をつけている小さな畑を少し誇らしげに指差しました。
「ああ、なるほど。」と温郎はいいかげんにうなずいて見せました。そして きっとこの畑をやりながらぼくがこのベンチに腰掛けているのを見ていたんだ。
そのとききっとだれかがぼくのことを名前で呼んだにちがいない。
「でもそんなことあったかなぁ。」と思い返してみましたが無駄でした。
温郎はこのベンチでのこととなると何もかもがぼんやりしてきて 昨日起こったことでももうあまり憶えてはいないのでした。
しかし名前のことはたぶんそうに違いないと温郎は考えました。そうなると もうこれからはこれまでのようにのんびりとした気持ちでこのベンチに座ってはいられないかもと思いました。
すると「温郎、そんなこと心配しなくてもだいじょうぶだ。私はまもなくここからいなくなるんだからな。」と清水老人は言いました。
「えっ。」と温郎は驚いて清水老人の顔を見ました。どうしてこちらの気持ちがわかるんだろうかと不思議でした。でもそんなことどうでもいいような気もしました。きっとこれくらいの老人になると簡単な読心術ぐらいできても不思議ではないと思えるほど中学生の温郎はこの老人を自分とはかけ離れた存在のようにかんじていました。
でもいなくなるとはどういう意味なんだろう。歳のことを言ってるのか。
確かにかなりの高齢ではあるもののこの人にはどこか年齢を思わせない活気が感じられて 少なくとも今日あしたどうこうという話でもないだろうと温郎は思いました。
(短編ファンタジー集|天ぷらしぐれ「川鯉がザブ」②に続く)