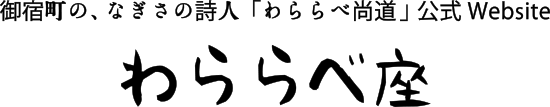短編ファンタジー集|天ぷらしぐれ「あかねやま交番所」

のっそりと バス横たわる 浜ぼうふう
のっそりと バスよこたわる はまぼうふう
※注釈
ぼうふうは俳句では春の季語になっています。
浜ぼうふうはセリ化ボウフウ族の多年草。日本の海岸の砂地に自生しています。
茎は短く、根元から出る葉には紅紫をした柄があり、花は6~7月ころに白い小さな花を多数密生させます。
果実は、楕円形で長さが4ミリ程度で軟毛が密生しています。
根は乾燥させ風邪、頭痛、関節縁などの薬用に用いられ、厚く光沢のある葉は刺身のつまやサラダなどにも用いられます。
1
山の若葉がまぶしい季節でした。むせかえるような山の青い空気を運転台のわきの窓を少しあけて感じながら前田さんはバスを走らせていました。
乗客はいません。今日は半島の南を巡ってホテルへお客を下ろした帰りでした。
ところが山深い道路を上って 谷川にかかった橋を渡ったときです。
「おかしいなぁ、こんなところに赤い橋なんてかかってたかなぁ。」
そう思う間もなくバスは両側を深い藪に包まれた見覚えのない薄暗い山道で突然止まってしまったのです。
「おや、どうしたんだ。どうして止まっちゃったんだ。おいおいこんなとこで勘弁してくれよなぁ。」
前田さんはぶつぶつとそれでも軽口をたたきながらアクセルを踏みなおしたり いろいろと試してみました。そこはこの未知三十年のベテランです。
「動かないはずはないんだけどなあ。」
そう言ってガソリンのメーターを覗き込んだ前田さんはぎょっとしました。
「おかしいな、こんなはずない。たしかホテルで客を下ろして間もなく国道沿いのガソリンスタンドで給油したはずなのになぁ。まさか。」
前田さんはバスから降りるとエンジンルームやバスの周囲を点検してみました。
「油がもれているなんてことはないようだし。」と 首をひねりました。
それから「さあて、どうしたものかな。」と言ってから運転席に戻った前田さんは制服のボケットからライム味のチューインガムを取り出すと一粒口に放り込みました。こんなとき去年まではたばこを一服やっていた前田さんでしたが、昨年心臓の病気で奥さんを亡くしてからというものたばこはきっぱりとヤめたのでした。
こうして眺めて見ると ただの竹やぶかと思っていたらなかなかどうして深い竹林でした。ウグイスのさえずりが林の中でこだましています。
風が笹の葉をさやさやとゆすってそれが潮騒のように聞こえています。
「しょうがない、会社に電話するしかないか。しかしガスケツとはな。」
それから前田さんは運転台の棚にある会社から支給されている携帯電話に手を伸ばしました。
ところが通じないのです。バスの会社はもちろんこんなとき助けに来てくれることになっているあの会社も自分の家も近くにある知り合いの家もだめでした。
どうやらどこにも電波の届かないようなところに来てしまったらしいのです。
「さあて、困ったぞ。」
前田さんはわざと大きな声でそう言ってみました。
こんなときなんだか意味もなくおかしくてふふっと笑いがこみ上げてきます。
「さてさて、どうしたものかな。」
前田さんはそう言うとバスから降りてみることにしました。
どこか近くの家を見つけてそこから電話を借りるしかないように思いました。
そうは言っても家などそう簡単には見つかりそうにはありません。
九十九折に上がっていく山道の両側には竹林と山つつじの低木が続いているばかり。
ところがいくらくねくねと山道を上り下りしてみても家らしいものは一行に見えて来ません。それどころかいいかげん歩いたかと思うと再び元のバスのある場所へ戻って来てしまいます。
そんなことを何度かやっているうちに午後の陽光も少しずつ西へ傾き始めていました。
それにしても不思議でした。
「確かにホテルを出て間もなく国道沿いのガソリンスタンドでバスを止めたはずなのになと前田さんは思いました。まさか止めるだけで油を入れてもらわなかったなんてことがあるだろうか。それとも本当は止めるつもりで通り過ぎていたのだろうか。
そういえばどんな店員が油を入れてくれたのかとかスタンドの様子などが全く思い出せないのでした。
奥さんが亡くなってからというもの前ださんは家の用事が急に増えていつも落ち着かない一方で気が付くとぼんやりと何もしないうちに一・二時間ほど過ぎているようなことが時々あるのでした。
「おれも歳かな、」
前田さんがそんなことを重いながら竹林の前を通り過ぎようとしたときでした。
薄暗い林の奥にわりと立派な倉庫らしきものがあるのを見つけました。
「あれはなんだろう、だれかが農具や機械をを閉まっておくために作ったものだろうかと思いながら足は自然とそちらの方に向いていました。
万一野宿などということになれば屋根があるだけましというものです。
ところが近づいてみると小屋には小さな看板がかかっていてそこには「あかねやま交番所」と書かれているではありませんか。
「へぇ、ここはあかねやまっていうとこなんだ。」と前田さんは思いました。
「ふうん、こんなところに交番があるのか。でもいったい誰がこんな場所で。きのこを採りに山に入って出られなくなったという話を聞いたことがあったけどもしも利用する人があるとしたらそのくらいだろう。」
板戸の横に赤い銅の風鈴がぶら下げてあります。
それを呼び鈴のつもりで鳴らしてみるとチリリンという思いのほか涼しげな音が響いて中から大きな黒褐色をした動物がぬっととがった鼻先を突き出しました。
前田さんは驚いて二・三歩後退りした拍子に笹の落ち葉に足をすべらせてしりもちを着いてしまいました。
「大丈夫ですか。」
その黒褐色をした大きな動物はそう言うと両手を出して前田さんを起こしてくれました。軽く手を引いてくれただけなのに前田さんはばね仕掛けの人形のように立ち上がっていました。
「ああ、すみません。どうも。どうやら家を間違えてしまったみたいで。」と前田さんが答えたのは大きな牡のいのししでした。
するといのししは「いえいえ、間違えてなんかいませんよ。ここでよかったんです。道に迷っていたんでしょう。みなさん最初は驚かれるんです。私のようなぶちょうほうな者が出てくるとね。」
「いやいや、そんなことは。」と前田さんは尻の土をはらいながらあわてて言いました。
そのとき前ださんはいのししの頭にちょこんと小さな赤いヘルメットが乗っているのに気づきました。ヘルメットには星雲状の粟の粒で8の字を横に寝かせたような見たことのない文字が印されています。
「どうしました。遠慮しないで話してみてください。だいぶお困りの様子では。」といのししは言います。
前田さんはなんだかいのししに道をたずねるのもしゃくで早くこの場から立ち去ることしか考えていませんでした。以前から前田さんはどうもいのししというものが苦手でした。この動物は一軒鈍重そうに見えてなかなかにすばしこい動きをすることも知っていました。大きな図体をしてその小さな目でほんとのところ何を考えているのかよく分からない油断ならないもののように感じていたのです。
それにバスの運転手としてはなんといってもこの道三十年のプライドというものがあります。
「いやいや、別に道に迷ったというわけじゃないんです。ただこんなところに家があったので珍しいと思っただけで。」と前田さんは言って今度は慎重に二・三歩後ずさりしました。
「そうでしたか。それは失礼しました。またこちらに来たときはお気軽にお立ち寄りください。」
いのししは小さな目を残念そうにしばたかせてそう言うと軽くお辞儀をしました。
そのときいのししの頭の小さな赤いヘルメットが落ちて前田さんの足元の方に転がって行きました。
「あ、落ちましたよ。」
前田さんは腰をかがめてその赤いヘルメットを拾い上げるといのししの頭の上に乗せてやりながら
「ヘルメットに何か書いてありますね。」と 聞くともなしに聞いていました。
「これは私たちいのししの世界の文字でしてね。この一文字で「時を巡回し警護する者」という意味があるんですよ。私たちはふだんはもう少し簡単にタイムパトロールと呼んでいますけどね」といのししは胸を張って言いました。
「えっ、たった一文字で。」
前田さんは少し驚いてそう言いました。
「そうです。これはなんていいますか、アルファベットのような表音文字ではなくて漢字のような表意文字なんですね。だから一目で
どういう意味かが分かるんです。どうです。なかなか進んでいると思いませんか。」といのししは言います。
「ううん、なるほどね。」と前田さんは言いましたが心の中ではそれなら文字というよりマークの一種じゃないか、こんなご大層なことを言ってもきっと子供の警察ごっこに毛の生えたものなんだろうと思っていました。
そして「そうだ。せっかくだからこのいのししに聞いてみればいいんだ。
タイムパトロールとか言ってるぐらいだから もしかしたらこれぐらいは知ってるかもしれない。」と思って
「あの、この近くに民家はありませんかね。つまり人間が住んでいる家ってことですけど。」と聞いてみました。
するといのししは気の毒そうに「いやあ、このあたりには人の住んでいる家っていうのはありませんねぇ。
せめて四・五年ぐらい前だったら一人暮らしのお年寄りが住んでいた農家が三軒ほどあったんですけどね。」と言います。
「そうですか。」と言うと前田さんはふっとため息を付きました。えらいところでえんこさせてしまったもんだとさすがの前田さんも少し弱気になりかけました。
そのとき交番所の中でだれかがくしゃみをしたのが聞こえました。
それはまるでラッパ水仙の先から飛び出してきたようなかわいらしいくしゃみでした。
「あっ、あれは娘でしてね。この時期は花粉症でいけないんです。」といのししは言います。
「へぇ、いのししも花粉症になるんだ。でもとてもかわいらしいくしゃみだったじゃないか。そういえばうちの奥さんも花粉症でこの時期は困っていたっけ。」と前田さんは思いました。
「お客さんだよ、おまえもこっちに出てきてごあいさつしなさい。」
「いえ、わたしのことなら気にしないでください。」と前田さんは言いましたが、すぐに小屋の板戸が開いて頭に白い花飾りを付けた
かわいらしいいのししの娘さんが出てきました。
「こんにちは、あかねやま交番所へようこそ。」と優しい声で娘さんは言うと「クスン」とまた一つかわいらしいくしゃみをしました。
「こんにちは、おじゃましてすみません。もうすぐに帰りますので」と前田さんが答えると、「今トルココーヒーをお持ちしますから少しお待ちください。」と娘さんは言ってまた交番所の中へ入っていきました。
コーヒーと聞いて前ださんは少し心が動きました。実はもうさきほどから喉がからからだったのですがいつもはバスに用意してある缶コーヒーもこんなときに限ってきらしていたのです。
「父親の私が言うのもなんですが娘の入れるトルココーヒーは絶品なんです。
「なにしろ母親の直伝でしてね。」
「ほお、そうなんですか。トルココーヒーなんて珍しいですね。私なんぞもっぱらインスタントばかりですよ。
それにしても母と娘が仲がよいというのはいいものです。」と前田さんは微笑しました。
するといのししは短い首を小さく振りました。
「いえ、あの子の母親はもういないんです。妻は去年の夏に心臓の病気で亡くなりましてね。」
えっ、「そうでしたか。それはそれは。」と前田さんは言いました。昨年の夏といい心臓の病気だというところまで同じじゃないかと前田さんは驚きました。
「妻はトルココーヒーを入れるのが上手でしてね。あの個がそれを引き継いでくれたのがせめてものなぐさめです。どうか飲んでいってください。」
2
少しすると交番所の中からコーヒー独特の香ばしいかおりが流れてきました。
「いいかおりですねぇ。なんといってもコーヒーは香りが一番です。」と前田さんは言いました。
「そうですね確かにこの香りはいいものです。でもトルココーヒーは香りだけじゃありませんよ。」といのししは言います。
板戸が開いて娘さんがトルココーヒーを乗せたステンレスのワゴンを押して出てきました。そのワゴンの上のティーカップを見て前田さんは驚きました。
とにかく大きいのです。どんぶりほどもあるでしょうか。
前田さんの前にもそのどんぶりほどの大きさの白いティーカップの乗ったワゴンが置かれそのカップの中で薄い黒褐色の液体の表面がさかんに泡だっていました。
こんなにたくさんは飲めないぞと重いながら「いいですね。いつもこんなおいしそうなトルココーヒーをいただけて。」と前田さんは言ってカップに手を伸ばしました。
すると父親のいのししが言いました。
「じつはわたしコーヒーは苦手でしてね。妻が生きていたころはもっぱら飲むのは母親と娘ばかりで私はいつも熊笹のお茶ばかりでした。それが今ではもうこれなしでは昼も夜も明けませんでね。」
すると今度は娘のいのししが言いました。
「私たちいのししには普通のコーヒーはちょっと物足らないんですが このトルココーヒーのどろっとした濃厚な味がなんともいえないんですよ。でもお客さんは初めてらしいので今回は少し薄めにしてミルクも入れてマイルドな物にしておきましたので。でも量が多かったら遠慮なく残してくださいね」
「ああ、そうでしたか。それはどうもどうも。気を使っていただいてすみません。」と前田さんは言いました。
「ああ、娘が言ったように量が多すぎたら本当に残してもらっていいんですよ。実はねお客さん、このトルココーヒーというのはね、なんといってもこの表面にある泡が最高でしてね。まずこの粟をゆっくりと味わって飲んでみてください。」と父親のいのししが言いました。
「そうですか。ありがとうございます。」
前田さんはそう言うとビールの大ジョッキのような大きな取ってを掴むと言われたとおりにカップの粟をまるでビールに口を付けるときみたいにすすりました。
「ううん、なかなかいい香りですね。」と前田さんは言いました。
「そうでしょう。この粟が最高なんです。身も心もふわりと暖かく包み込んでくれるみたいでなんともいえない気持ちになりますからね。」
言われてみると確かにそうでした。ふわりとした粟をすすると口の中でコーヒーの濃厚な香りが広がったかと思うとその香りがどこまでも広がって自分のからだ全身を包み込んでまるで自分がコーヒーの粟の中に入ってしまったような感覚になるのでした。
「うん、これはなかなかいい感じですね。」と前田さんは大きくうなずきました。
「そうでしょう、そうでしょう。私はこのふわりとした暖かなコーヒーの香りに包まれているとなんだかこれに似たことがこれまでいくつもあったことを思い出しましてね。たとえば亡くなった妻のこともそうです。彼女は元来気持ちの清らかな女でしたが ときにはなかなか手厳しいことも言ったものです。でも今思い出すことは彼女の優しい顔ばかりです。ああそうそう、こんなうららかな陽気のときはよく妻に頼まれてシーツの洗濯を手伝ったもんですよ。なにしろ私たちの使うシーツというのは大きいですからね。一人ではなかなかうまく干せないのです。だから二人でシーツの端を引っ張ってピーンと伸ばしてやるんです。まるでローラーにかけたみたいに皺一つなくきれいに干せますからね。その後は妻がていねいにアイロンで仕上げてくれます。彼女はアイロンがけが上手でしてね。そうやって仕上げたシーツにくるまって寝ていると本当にいい夢を見ることができるんです。そういう妻の優しさや春の日差しのことや秋の林の木漏れ日の暖かさや、まあいろいろなことをこのコーヒーの粟は思い出させてくれるんです。」と父親のいのししは言いました。
前田さんはとうとう最後まで自分の奥さんのことを話すことができませんでした。
いったい自分は彼女にどんな優しい気持ちを表現できただろうかと思うと簡単に私の妻もおなじころに亡くなりましてねとは言い出せなかったのでした。
こうしてトルココーヒーの粟をすすっていると前田さんにもいのししの夫婦が竹林で大きなシーツの端を持って引っ張っている光景が浮かんできます。
お互いに呼吸を合わせてシーツを引っ張ったときに鳴るパン・パンという音が竹林にこだまする音が聞こえたような気がしました。
私などシーツの一枚はおろかシャツの一枚も手伝ってやったことはなかった、自分に比べてこのいのししはなかなかりっぱじゃないかと前ださんは思いました。
とうとう前田さんは正直にバスが動かなくなってしまったことを話しました。
「どうしましたか。エンジンでも故障したんですか。何なら部品の一つや二つ何とかなるかもしれませんよ。」
「いや、故障といいますか、ちょっとお恥ずかしい話ですがガスケツでしてね。ガソリンを入れたつもりでいたらそうじゃなかったんですよ。自分でも何をやってるのかわけがわからなくなりましたよ。」
気が付くと前田さんはいのししに向かって今日のことをあれこれとこぼしていました。
「しかしほんとうに油は入れてなかったんですか。ポケットにガソリンスタンドのレシートとか何か入っていませんか。」
いのししにそう言われて前ださんははっとしました。
「そうだ、どうしてそれを確認しなかったんだろう。」と思いました。
試しに紺のズボンの尻ポケットに手を入れるとガソリンスタンドのレシートが出てきたではありませんか。
「ああ、やっぱり油は入れたんだね。でもそれならどうしてだろう。」
前田さんは首をひねりました。
「ははあ、なるほど。実際にはスタンドでガソリンを入れたのにその記憶があいまいでほどんど憶えていない。しかも実際車には入っているはずの油が入っていないというわけですね。これはおそらくお客さんがうっかりして時間軸の平行道路に入り込んでしまったせいでしょうね。」といのししは言います。
「はっ、時間軸のなんですって。」と前田さんは大きな声で聞き返しました。
時間軸の平行道路ですよ。つまりこの世界というのは普通に生活している空間と平行して別にいくつもの並行する空間がありましてね。学者は平行宇宙とか呼んでいますけれども、道路も同じでしてね。いつも使っている道路とは別に時間軸に平行していくつもの複数の道路というものが走っているんです。もちろん普通はそうした道路に迷い込まないようにガードレールのようなもので仕切られているんですが、まるで高速道路のインターチェンジのように並行道路に出入りするすきまのような空間があるんですよ。それが調度このあたりにも
ありましてね。」
いのししがそういい終わらないうちに前田さんは駆け出していました。竹林を飛び出して道路に立って周囲を見回しました。
それから首をひねりながらまたいのししのところに戻って来ました。
「今見てきたけど、別に並行道路なんてものはなかったよ。」と前田さんは言いました。
「ああ、そうなんです。別に目に見えるものではないんですよ。人間が作ったアスファルトの道路とは違いますからね。でも私たちいのししにはそれが見えるんです。まあ神様からいただいた能力ということなんでしょうかね。」
いのししがちょっと自慢げにそう言ったので前田さんは少しいやな気がしましたが こうなってはその時間軸の平行道路のなんとかという話にすがるしかないようにも思えて
「というと私はその平行道路に迷い込んだってわけなんですか。」とたずねました。
「そうかもしれませんね。私の経験ではだいじな場所を通過するときにぼんやりと自分がなにをしているのかしっかりとした記憶を持たないままそこを通過してきたりすることがあるとそういうトラブルにみまわれることが多いようです。」
「え、多いようですって。こういうことはこれまで何件かあったわけ。」
「そうです。さっきも言いましたがこのあたりは平行道路にぬける一種のインターチェンジのような場所になっていますからね。お客さんのようなケースがときどきあるんです。まあそのためにといいますか、そういうときのために私たちはタイムパトロールという仕事をさせてもらっているわけなんですがね。」
いのししはそう言うと頭の上の赤いヘルメットにに手をやりました。
「ふうん、時間軸の平行道路ねぇ。」
前田さんはなんとなくまだ腑に落ちないという顔でそこにハイウェーか何かが走っているかのように竹林の狭い空を見上げました。
3
「つまり私がどこかに置き忘れてきてしまったガソリンスタンドでの記憶を見つけてくれば問題は解決するということですか。」
前田さんがそう言うと
「そうです。そしてそれを取りに行くのが私たちタイムパトロールの仕事でもあるんです。」
「え、取りに行くって。でもあそこまで行くとしたらけっこう遠いですよ。車か何かあるんですか。ああ、パトロールっていうぐらいだからきっとパトカーとかあるんでしょうね。」
前田さんがそう言うと、いのししは短い首を激しく振って
「いえいえ、そんなものは必要ありません。私たちはひたすら走るんです。黒いからだをまるめて弾丸のように一直線に飛ぶように走って行くんです。頭の中を真っ暗にして無念無想の気持ちで走るんです。少しでもつまらない邪念が入るとうまく行かないものですからね。」といのししは言います。
「へえ、そういうものなんですか。」と前田さんは修行僧でも見るように黒褐色のいのししをながめました。
「さあ、憶えている範囲のことでかまいませんからそのガソリンスタンドがどこにあったのかできるだけ詳しく教えてくれますか」と
いのししは言いました。
「はあ、そういうことならもちろん。」
前田さんが半島の南の端の町のホテルでお客を下ろしてから間もなく入った国道沿いのガソリンスタンドについてできるだけ詳しく話そうとしましたがガソリンスタンドの場所についてはなんとか説明できたもののスタンドでどうしたのか、それから後のことはだれかが頭の中の記憶の歯車を一本抜き取って行ったかのようにみごとに思い出せないのでした。
「だめですね。うまく思い出せません。」と前田さんは頭を振りました。
「ええ、まあその程度わかればなんとかなるでしょう。」
「そうなんですか。すみませんね。」と前田さんは言いました。
「それじゃあ、私が今からそれを取りに行って来ますから。」
いのししがそう行って頭の上に手をやると軽く赤い小さなヘルメットの縁をさわりました。するとヘルメットは大きく広がってイノシシの大きな頭にすっぽりと収まりました。
交番所に入った父親のいのししが中で娘さんとひとこと二言話しているのが聞こえました。今からお父さんは仕事でひとっ走りしてくるからねとかなんとか言っているようでした。
それからいのししは先ほどとは違ったひきしまった表情で交番所から出てきました。
手には何か青黒いゴムの切れ端のようなものを持っています。
そしてそれをガムでも放り込むように口の中に入れました。
「これはホンダワラという海草でしてね。これを口の中でかみながら走ると無念無想でうまく走ることができるんです。」
いのししは小さな目を一瞬細めてそう言うと前田さんが声をかける間もなくからだを丸めて風のように走り出していました。
黒い大きないのししのからだはたちまち黒い弾丸となって竹林の奥に消えて行きました。
いのししが行ってしまうと前田さんは何かそこに取り残されたような気がしました。娘さんがいるはずの交番所の中もしんと静まり返って物音一つ聞こえてきません。さっきまでいっしょにトルココーヒーを飲んでいたはずなのにあの大きな白いティーカップもステンレスのワゴンもいつの間にか片付けられていました。
「あれ、どうしたんだろう。いったいぜんたいみんなどこに行ってしまったんだろう。」と前田さんはつぶやきました。
「どうしておれ一人のこしておまえはいっちまったんだ。世の中の何もかもがおれを残していっちまったんだ」
いつのまにか風が増して前田さんの頭上で笹野はが潮騒のように響いていました。
前田さんは自分が何か風に揺れる竹坐作の一本になったかのように その寄る辺のなさに震えていました。
それからどれくらい経ったでしょうか。もしかしたらものの五分ほどだっったかもしれません。交番所の中で「クスン」という娘さんのかわいいくしゃみが一つ聞こえて前田さんははっと我に返りました。
竹林の風がぴたりとやんで遠くから馬の大群が大地を踏み鳴らして近づいてくるような音がしました。それはしだいにこちらに向かって来るようでした。でもそれは馬ではなくいのししの大群でした。何頭ものいのししが何本もの平行ドウロを横に肩を並べてこちらに向かって突進してくるのが遠くに見えたような気がしました。
でも間もなくそれは大群ではなくたった一頭のいのししであることがわかりました。
「お待たせしました。」と竹林の入り口で声がしたかと思うと もう さきほどのいのししが前田さんの前に立っていました。呼吸一つ
乱れることもなく銭湯から今出てきましたとでもいうようなさっぱりとした顔をしています。
「やあ、すばらしく早かったですねぇ。」
前田さんが感心したようにそう言うと
「ええ、今日は全く無念無想で弾丸のように走ることができましたからね。全然疲れませんでしたよ。」といのししは言いながら頭の赤いヘルメットに手をやって元のように小さくつぼめました。
そのときヘルメットの中から何か薄い氷の破片のようなものが出てくるのが見えました。
いのししはそれを大事そうに手に取ると
「ありました、ありました。これがお客さんの落として言った記憶の断片です。調度お客さんの言っていたガソリンスタンドの裏の平行道路のどぶ板の上に落ちているのがすぐわかりました。間を置かずに取りに行ったのがよかったんですね。なにしろまだ今日の今日ですからね。これが何日も経ってしまうとひからびて光を失ってしまうので見つけるのもたいへんなんですがね。」
「はあ、それはそれは、どうもすみませんね。これがその私のあれですか。」
「そうです。」
いのししはそう言うとその薄い氷の破片を前田さんの差し出した手のひらに注意深く乗せて言いました。
「これを口に入れてゆっくりと舌で溶かすようにして飲み込んでください。」
「えっ、これをですか。」
「そうです。急いで歯で噛み砕いたりしてはいけませんよ。」
「そうですか。」
前田さんはここまで着たらだめもとで何でもやってみるしかないだろうと腹を決めて口の中にそっと入てみました。それは氷というよりは味のない平べったい飴のようでした。飴は舌の上でゆっくりと溶けて最後にごくりと唾液といっしょに喉の奥に消えて行きました。
するとどうでしょう。前田さんの頭にあの国道沿いのガソリンスタンドの光景が浮かび上がって来たではありませんか。
体格のいいごま塩頭の五十年配の男性の店員が出てきて応対しています。
鍵が渡されてバスのタンクにガソリンが入っていく音を聞きながら前田さんはその中年の店員と天気のことやこの町で毎年盛大に行われる
鯨祭りのことなど話しています。
そうだった、そうだったと前田さんは何度も深くうなずきました。
「どうやら思い出したようですね。」といのししが言いました。
「ええ、すっかり思い出しましたよ。」と前田さんはうれしくなってそう言いました。
「思い出すっていうのは案外うれしいことですね」
「ええ、そうですとも。みなさんそうおっしゃいます。そう言っていただけると私も走ったかいがあるというものです。」
「ええ、本当にご苦労様でした。ええと、それでつまりこれで。」
「そうです。たぶんもう大丈夫だと思いますよ。ご自分で確認していただければと思いますが。」
「ほんとですか。それならいいんですが。」
前田さんはそう言うと竹林を出てドウロの端に止めてあるバスまで端って行きました。
ドアを開けるのももどかしく運転台の前を覗き込むとガソリンのメーターは充分なところを差していました。
「ほお、これはこれは。」
前田さんはいのししのところまでまた走って帰りました。
「どうやらうまく行ったようですね。」といのししは前田さんの顔を見て言いました。
「やあ、ほんとうにうまく行きましたよ。不思議なことがあるんだなぁ。飴をしゃぶるとガソリンが満タンになるなんて。」
「記憶を取り戻した時点でお客さんはあのガソリンスタンドからもう一度へ行こうドウロを出てこちらの世界にバスといっしょにもどって来たんですよ。」
「そうですか。まあよくわからないけれどそういうことなのでしょうね。」と前田さんは微笑しました。
バスの所まで来て父親と娘のいのししが並んで見送ってくれました。
「どうぞ、お気をつけて。」と娘のいのししは言うとまた「クスン」とかわいいくしゃみを一つしました。
「ほんとうにこの時期はよそゆきになりませんでね。」と父親のいのししが言いました。
「何かいいお薬ってないんですか。」
「まあ、ないこともないんですが、海辺の方なのでついつい遠慮してしまいましてね。」
「海辺ですか。海辺の方にいい薬局でもありましたっけ。」
「いえ、薬局というんじゃありませんよ。この時期に浜辺に小さな白い花を着けている浜ぼうふうというかわいい野草があるんです。この草の根っこがいのししの花粉症には特効薬なんだっていう話を聞いたことがあるんですが、なかなか海辺まではねぇ。」
「そうなんですか。じゃあ今からいっしょに行きましょうよ。バスに乗って行けばだれにも知れずにすむじゃないですか。なあに、さっと浜辺に下りてやることだけやってさっとバスに乗って帰ってくればだれもわかりはしませんよ。」と前田さんは力強く言いました。自分でも驚くほど前田さんはこのいのししの親子に何かをしてあげたいという気持ちになっていました。何がなんでもこの親子をバスに乗せて海へ連れて行ってやるんだという強い気持ちがふつふつとさきほど飲んだトルココーヒーの粟のように沸いてくるのを前田さんは抑えることができませんでした。
「いやあ、そうですかね。なにしろ私ども人目を引くものですから。」
「だいじょうぶですよ。少し日の暮れた時分に行けばね。」
「いやあ、そうですか。それならおまえ、いっしょに行ってみる会。」
父親のいのししがそう言うと、娘の顔がぱっと輝きました。
「ええ、そうですね。わたし一生に一度は海というものを見てみたいとは思ってました。それはそれは広いものなんですってね。向こう岸が見えないほどどこまでも水の原が続いていて、何本も川がそこに注いでいて、海の中にもまた川が流れているって私にはどんなものか
とても想像できないんですよ。
「」
「ああ、そうでしたか。海というのはね。」
前田さんはそう言い掛けて言うのをやめました。
海を見たことのない者に海を説明するのはなんてむずかしいのだろうと思ったからでした。
「お父さんもずいぶんしばらくぶりなんでしょう。あれもそろそろ無くなってきたみたいだから調度いいんじゃないの」と娘さんが言います。
「あれってなんですか。」
「例のホンダワラです。お客さんの記憶を取りに言ったとき口の中に入れていたやつです。」
「ああ、あれですか。海水浴をしているとときどき足にからみついてくるやつですね。あんなものだったらいくらでもありますからね。」
「お母さんが話していたことがあるんですよ。昔お父さんといっしょに海へ出かけたときにお父さんがかってにどんどん海に入って行ってもうこのまま帰ってこないじゃないのかって心配してたらあのほんだわらの海草を背中にたくさんしょって泳いで帰ってきたって。それがまるで海辺のライオンのようにりりしく見えたって。それはもうお母さんの一つ話みたいにね。」
ほどなくして西日が竹林の奥に深々と差し込んでくるとバスのエンジンの音が高らかに鳴り響きました。いのししの親子はからだをまるめてバスに乗り込みました。前田さんの運転するバスは海辺へ向かって九十九折の山道を下って行ったのでした。
(終わり)
のっそりと バス横たわる 浜ぼうふう