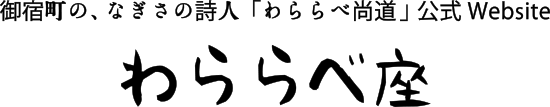11. ノベンバーソングス
ノベンバーソングス 詞・曲 わららべ尚道
十一月の草原 ベンチに男が一人
自分の名札を捨てたくて 風の歌を聞く
約束に疲れて 空の深さが恋しくて
知らず 身を 横たえば 百舌鳥の声がしたパーカーのポケットから 貝殻を取り出して
思い出伏せるみたいに 胸の上に置いて
ちっぽけな花野摘んで きみにきみに 贈る夢
秋の日が男を置いて 山のねぐらへ帰る十一月の浜辺に 裸足の女が一人
焦げついたこころ抱えて 波の歌を聞く
約束に疲れて 海の広さに抱かれたくて
足を波に浸せば 鉄橋の音がした空色のポシェットから 押し花を取り出して
蝶々飛ばすみたいに 潮風に放して
薄紅の貝殻拾って きみにきみに 贈る夢
秋の日の風の寒さが 女を町へ帰す十一月の公園 子猫と老犬が一組
日だまりにうずくまって 遠くの歌を聞く
冬が来れば少しは 人恋しくなるのかと
たがいの飼い主について どうしたものかと話すポプラの木の下から 貝殻を取り出して
何かしら答え探して 眺めてはあきらめる
ちっぽけな花のような生命 きみに贈る歌
秋の日が 急に陰って それぞれの家路に帰すちっぽけな花のような生命 きみに贈る歌
秋の日が急に陰って それぞれの家路に帰る
「ノベンバーソングス」には2人と1組の主人公が登場します。
草原の男、浜辺の女、公園の子猫と老犬、それぞれが独立した歌の世界をたもちながら、それぞれの世界はどこかでつながり呼応しています。
男が手にしている貝殻、そして花を送る夢、女が拾った薄紅の貝を送る夢、潮風にむかってまいた押し花、子猫と老犬がポプラの木の下から取り出した貝殻、彼らが手にしているこれらの物たちの存在が、彼らの宇宙がどこかでつながり呼応していることの証拠です。
それらは、シンクロニシティ(意味ある偶然)によって時空間を超え、届けられた物たちです。
この作品ができたきっかけは、ねじめ正一の恋愛小説「荒地の恋」 (2007年 文芸春秋)を読んだことでした。
戦後間もない1947(昭和22)年9月から翌年6月、詩誌『荒地』が創刊。詩誌の中心メンバーであった北村太郎、田村隆一、鮎川信夫などの、戦後を代表する詩人たちが実名で登場してくる小説です。
1976(昭和51)年、北村は新聞社の校閲部で働きながら、細々と詩作を続けていました。
妻の治子、娘の優有子、息子の尚と共に、平凡だけれどもしっかりと家庭を支えて堅実な生活を送っていたのです。
しかし、そんな北村に大きな転機が訪れます。友人である田村の妻・明子と頻繁に会うようになります。
明子に対する感情を抑えきれなくなった北村は仕事も家庭も全て捨てて、同じように家を出た明子と共に暮らすようになります。
明子との暮らしの中で、これまで寡作だった北村は多くの詩を生み出していきます。
小説「荒地の恋」の終わり近くに「八月の林」という詩が提示されています。
「八月の林」 北村太郎
うらみごとを いわせぬ速さで
風は来たり、風は去り
林は、もとのままに静まって
大いなる感情を、しっかり守っている
下生えは、倒れ伏し
みどり色を、みずからの乱れに逆らって
整えなおそうとし、しかし
ホタルブクロなどは、かしいだまま
花を垂らして、揺れに耐えている
あまりの暑さに、物のにおいも
においのなかに、こもってしまい
ヘビやチョウのたぐいが、林の
神経のように、かろうじて
働いているようだけど、見えない麦藁帽子を、ひざに置き
下の、池のほとりのベンチに座る男を
林ぜんたいが、気づいていて
知らぬふりのまま、遠ざけており
男は、うなだれて動こうとしない
足もとにミョウガが、踏まれてあり
池はアオミドロの顔で、男を
しげしげと見つめながら、泡ひとつ
立てるでもなく、重さを保っている
ひどい暑さが、水面を緊張させて
虫いっぴきの飛び出しをも、けっして
許そうとはせず、男の
眠りを、眠りの手でゆっくりかきまわし
ずれているひざの帽子を、落とさせないけさ、ヒグラシが鳴いていて
夜なかの風は林の追憶を、いっそう
ゆたかにし、いじわるにもした
真昼、おびただしい葉は力いっぱい広がり
真上の日輪よりつよく、影を消している
(※平成5年 思潮社「すてきな人生」から)
「八月の林」は、悪性リンパ腫にかかった北村太郎が、死の2か月前に作った詩なのだという。
この作品は北村太郎の代表的な作品として評価が高い。
ねじめ正一も
「結局あれだけいろいろあったけど、最後に一番いい詩を書いた。人生は暴走したけど、最後に『八月の林』という詩を書いてしまった。死ぬ前の本当に最後の作品ですね。これが最高、私は一番いい作品だと思っているんですよ…」
などと言っています。
(「有隣」第490号 平成20年9月10日、「座談会:これからの老後」より)
実はノベンバーソングスはこの「八月の林」という詩に触発されて生まれた作品です。
決して大向こう受けするものではありませんが、この詩には読む人の中にある静かな衝動を揺り動かしてくれる不思議な力があります。
世界に向かって自己を立ち上げてきた力がゆっくりと失われて、世界は静寂に向かって動きを停止します。
しかしそれは生命力の枯渇を意味するものではありません。
「真昼、おびただしい葉は力いっぱい広がり 真上の日輪よりつよく、影を消している」
という表現でこの詩が締めくくられていることでもわかるように、それはむしろエネルギーを満々とたたえた静寂なのです。
人は何か成ることを求めひとかどの人物でならんとします。
その目的に向かって自己を立ち上げ、努力をします。
しかしそれは、ただ在ることの至福、実から人が世界を認識し、表現し、成長する、という本来の実存に根をおいた真の意味での成ることを、在ることという実存的な生から分離させて、本来の人間の存在を阻害してしまうのです。
しかしこの「八月の林」が描いている世界は、それとはまったく真逆であり、
在ることから分離しかけた、成ることへのあらゆる動きを止めさせて、在ることの中に引き戻しエネルギーに満ち溢れた静寂を保っているのです。
この「八月の林」を読んだ時、私はアトバイタ、非二元論のニサルガダッタのことばを想起しました。
以下はニサルガダッタの「私は在る」からの引用で解説を閉じたいと思います。
「すべての分割はマインド(チッタ)のなかにあり、実在のなかに分割(チット)はない。
運動と休息はマインドの状態であり、互いに対極なしには存在できないのだ。
それ自体では、何も動かず、何も休息しない。」
ーーー中略ーーー
「マインドを超えたところに体験はない。体験とは二元的状態だ。
実在を一つの体験として語ることはできないのだ。
ひとたびこれが理解されたならば、
あなたはもはや、在ることと成ることを分離し、対立したものとして追い求めたりはしないだろう。
実際には、同じ木の根と枝のように、それらは一つであり分割不可能だからだ。
そのどちらも意識の光のなかにのみ存在することができ、
どちらも「私は在る」という感覚の中に立ち現れる。
これが基本的な事実であり、
もしこれを逃したならば、全てを逃すことになる。」「27 はじまりなきものは永遠にはじまる」より抜粋
(※「アイ・アム・ザット 私は在る―ニサルガダッタ・マハラジとの対話」ナチュラルスピリット・パブリッシング 80 刊)